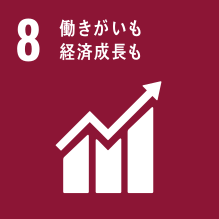アルティウスリンクでは、現在600名以上の障がいのある方が、コンタクトセンターをはじめとした全国各拠点で活躍しています。その所属する部署は、コンタクトセンターなどの基幹ビジネスの部署が8割、障がい者雇用専門部署が2割(さらに特例子会社・株式会社ビジネスプラスも別に運営)と、コミュニケーションが得意でない方や多くの人のなかでの就業が難しい方など、基幹ビジネス部署での就業が難しい方でも活躍できるよう、専門部署を設けて環境を整えてまいりました。
東京(新宿)を拠点とする「事務サポートユニット」は、社内の事務・庶務業務の代行や印刷、社内便の業務を行っています。2016年のユニットの立ち上げから現在に至るまでさまざまな取り組みを行っているほか、障がい者雇用に取り組む企業に対し見学会も開催しています。この度、取り組みを紹介する2つのイベントにオファーをいただき、ユニットを代表して村上ユニット長が登壇した模様をご紹介!
前回のとっとり就労支援フォーラム編に引き続き、今回は東京で開催されたキャリア自律支援イベントをご紹介いたします。

<左:とっとり就労支援フォーラム(鳥取)/右:キャリア自律イベント(東京)>
■若者が働きたくなる職場・辞めたくなる職場の違いは?~キャリア自律イベント~
二つ目の登壇は、株式会社リクルート主催の人事・経営者向けセミナー「若者が働きたくなる職場・辞めたくなる職場の違いは?~キャリア自律支援を起点とした採用成功・定着の新潮流~」のパネルディスカッションにお招きいただきました。
このイベントは「『キャリア自律支援』の課題と処方箋を探る」をテーマに、企業としてキャリア自律をどのように支援し、組織と個人の未来をつなげていくのかを議論する会としてオンライン限定で開催、同時接続で約200名にご視聴いただきました。

<左から、水野氏、坂井氏、加山氏、村上ユニット長、藤井氏>
パネリストには、株式会社Momentor代表取締役の坂井風太氏と株式会社丸井グループ人事部人事課 課長の加山洋善氏。そして、株式会社リクルートからHR統括編集長の藤井薫氏と研究員の水野理哉氏が進行役として参加。また、今回の登壇は、リクルートが運営する『リクナビNEXT』主催の「第10回 GOOD ACTIONアワード」※1における『Cheer up賞』の受賞がきっかけとなりご縁をいただきました。
第10回 GOOD ACTIONアワード『Cheer up賞』受賞
第一部では、リクルートの水野氏より「キャリア自律調査から見えてきた課題と示唆」のテーマで事前調査の結果とキャリア自律支援の課題が報告され、その後、第二部で村上ユニット長がキャリア自律支援に取り組む企業として丸井グループの加山氏と共に経験談をお伝えし、Momentorの坂井氏からご意見をいただくディスカッションへ進みました。この模様は、リクルート公式サイトにてご紹介されています。ぜひご覧ください。
ここからは、登壇のなかで伝えられた村上ユニット長のコメントを中心に内容の一部をお届け!
意見交換がされた4つのテーマのなかから、①と④について紹介します。
①「キャリア自律支援のしくじり体験について/悩みどころと乗り越え方」
②「キャリア自律支援の手応えや成果」
③「従業員は“主体性がない”は本当か?」
④「これからの時代のキャリア自律・支援のあり方」
■「理論のポップ化」その言葉で取り組みのポイントを再認識
冒頭に障がい者雇用専門部署での取り組みになるため、一般的なキャリア自律支援と異なる可能性を伝えつつ、取り組みが活用のヒントになればと伝えました。
- 知識の習得が自分を助ける武器となる
一つ目のテーマ「キャリア自律支援のしくじり体験について/悩みどころと乗り越え方」をお伝えする場面では、業務体制づくりに注力したことでキャリア支援が出遅れたことを反省しながらも、働く仲間と”共に歩く”視点を持てたこと、さらに苦労したポイントを知識の習得によって乗り越えたことを振り返りました。
“可能性にバイアスをかけない“という想いで挑戦した「チューター制度」は、入社後の不慣れな環境下で変調が現れやすい新人を、自らも障がいのある先輩がサポート・育成するため、さまざまな特性の理解や、意思疎通の姿勢、指導方法を学習し、さらにチューター自身にかかる心的負担を取り除く工夫や体制整備などの課題がありました。この課題に対し、心理学の理論である「認知のゆがみ※2」に踏み込み、「一般化のしすぎ」「拡大解釈」「すべき思考」などが教える側だけでなく、教わる側にもあることをユニット内の全員が理解できるようマニュアルを整備。その際、起こりがちな”あるある“を漫画化して展開し、理解促進につなげたことを伝えました。また、自身の得意・不得意、助けが必要な場面を言語化した自己紹介シートである「わたしのトリセツ」についても、お互いが事前知識を持つことで会話の糸口や教え方・教わり方のヒントが得られる好事例として紹介。各々が知識を習得することで自身を助ける武器となることに早く気がつくべきだったとしました。
この点に対し、坂井氏より「村上さんの取り組みで素晴らしいのは『理論のポップ化』だと思います。理論として認知のゆがみのパターンを挙げるのは難しいですし、『漫画』や『トリセツ』として伝えることで従業員の抵抗感を減らし、会社からの押し付け感もなくしている点が良い」と取り組みのポイントを再認識できるようなコメントをいただきました。

<配信会場では登壇者5名の濃密なディスカッションが繰り広げられました>
- 過干渉になり過ぎず自律を促しながら並走する支援
四つ目のテーマ「これからの時代のキャリア自律・支援のあり方」では、双方向の対話を愚直に続けていくことがキャリア支援のベースだとしました。相手が本心で話ができるよう日頃の接点を増やし、密度の高い関係性の構築を目指していることに触れ、普段から雑談ができない関係性では、本音を引き出せないと伝えました。また、そのことを管理者同士で理解し合い、フランクな場面も作りながら良い関係性・良いチームになるよう努めているとしました。その関係性がしっかり作られた前提で「次はどんなことに挑戦したい?」という将来のありたい姿について話をし、その回答を基に管理者が実現に向けてどのようなサポートができるかを考えるようにしているとキャリア支援に対する考えを述べました。
そして、「過干渉になり過ぎない」ことも重要視しているとし、障がい者であっても社会人であることを念頭に置いて欲しいため、会社や仲間との関り方について考える機会や行動評価を受けることで社会人の基礎力を備えつつ、上長として将来を共に考えていく、そういうチームでありたいと伝えました。さらに、その先に面白そうな取り組みを見出せたら、全員でチャレンジしていきたいとまとめました。

<イベントの終わりに登壇された皆様と一緒に記念撮影>
イベントにご参加いただいた皆様、関係者の皆様、貴重なお時間をいただきありがとうございました!
■一番大切にしていることは公平で丁寧な対話
今回の2つのイベントだけではなく、社外の方へ事務サポートユニットの取り組みをお伝えする際、「一番大切にしていることは公平で丁寧な対話」であることを必ず伝えている村上ユニット長。実際に事務サポートユニットでは、メンバー全員に対し、契約更新の面談からはじまり、不調の申告時、トラブル発生時、ミス多発時など細かく・頻度の高い面談で丁寧な対話を行っています。また、管理者との面談だけでなく、就労支援機関を交えた面談など多方向からサポート。会社以外で見せる顔も知るようにしています。そして、面談を実施する際には、穏やかさ、誠実さ、温かさをもったうえでの冷静さの維持に努め、面談前に抱えていた不安や心配ごとを一つでも減らすよう対話を行っています。
最後に、今回のイベントを通じて「リクルート様の調査結果や、他社の取り組み・専門的なお話などを伺い、学びの多い時間になりました。その中で、私たちが人間関係の構築を大切にしていること、それをベースにメンバーがキャリア実現できるさまざまな工夫をしていることを知っていただける良い機会になりました!」と村上ユニット長は振り返りました。

<2025年8月に移転した新しい職場で事務サポートユニットのメンバーと共に!>
アルティウスリンクは、今後もDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)を推進するとともに、従業員の活躍や職場の取り組みを発信してまいります。
- ※1.「GOOD ACTIONアワード」は、「働く個人が100人いれば、100通りの働き方があり、それぞれの働き方に合ったGOODな取り組みが存在する」という考えで、働くあなたが主人公となり、想いを持って始めた取り組みが、少しずつ周囲の人を巻き込みイキイキと働ける職場の共創へとつながる可能性を秘めた取り組みに光をあて応援する『リクナビNEXT』主催のアワードです。
https://next.rikunabi.com/goodaction/ - ※2.「認知のゆがみ」は、物事の受け止め方や解釈に偏りが生じる状態を示す心理学で活用される理論。